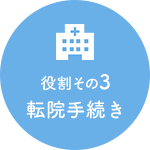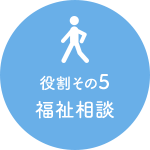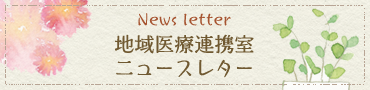地域医療連携
地域医療連携

- 看護師 2名
- 精神保健福祉士 4名
- 保健師 1名
地域の医療機関には、それぞれの専門性と役割があります。「地域医療連携」とは、地域の医療状況にあわせ、各医療機関が持ち味をいかして連携し、役割を分担して専門性を高め、医療機関ごとの機能をより有効的に活用すること。この地域医療連携によって、地域の患者さんが継続的に適切な医療を受けられるようにします。
未来の風せいわ病院の地域医療連携室では、病院と地域をつなぐ医療福祉機関の窓口として、適切・丁寧・スピーディな連携を目指しており、主に以下の業務を行っています。
地域医療連携室の主な役割
- 初めての方からの
お問い合わせ・ご相談の対応 - 当院へ初めてお問い合わせいただく場合のご相談窓口です。
ご本人やご家族、行政や学校、他の病院など、地域のさまざまな人々や機関からご相談をいただいています。気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 初めての方のご相談窓口(地域医療連携室)
-
TEL:019-696-2055(代表)
FAX:019-696-4185

詳しくはこちらをご覧ください
- 初めてご来院される
患者さんの受診・入院の日程調整 - ご相談窓口にご連絡をいただき、当院に受診をされることになった場合の、初診の日程などを調整いたします。入院されることになった場合も、こちらで調整して手配をいたします。
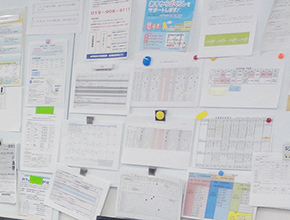
- 転院が必要な方の
日程調整と転院手続き - 他の医療機関からのご紹介で当院に入院される場合や、逆に当院の退院後、他に転院する必要がある場合は、その医療機関と連携し、スムーズに移動できるよう調整し手続きいたします。

- 通院患者さんの在宅療養支援
- 患者さんのご自宅での生活をサポートするため、ヘルパーの利用や施設サービスをご紹介します。また自立した生活を支援するために作業所や相談支援事業所のご紹介も行っております。

- 通院患者さんの福祉相談の対応
- 患者さんやご家族の方からの医療費の経済的問題に関するご相談や、社会福祉制度などのご利用についてのご説明を、精神保健福祉士が対応します。

地域医療連携室ニュースレター
地域医療連携室の取り組みをご覧いただけます。